
累計4万人以上の方が挑戦
ビジネスコンプライアンス検定
ビジネスコンプライアンス検定は
受け身の「法令遵守」にとどまらない
「社会的要請に応えること」としての
コンプライアンスへの深い理解と
活用能力を証明します。
受け身の「法令遵守」にとどまらない
「社会的要請に応えること」としての
コンプライアンスへの深い理解と
活用能力を証明します。

公開試験日程
第42回
2025年5月25日(日)
受付終了
第43回
2025年7月27日(日)
申込
受付中
受付中
お知らせ
- 2025/05/13
- ビジネスコンプライアンス検定 2025年7月27日公開試験のお申込受付を開始しました
- 2025/05/01
- 「2025年度夏期コンプライアンスオープンセミナー」開催のお知らせ
- 2025/03/18
- サーティファイ コンプライアンス検定委員長 郷原信郎 弁護士 新刊のご案内
- 2025/03/11
- ビジネスコンプライアンス検定 2025年5月25日公開試験のお申込受付を開始しました
- 2024/11/05
- ビジネスコンプライアンス検定 2025年2月2日公開試験のお申込受付を開始しました
(法令+倫理) × 責任 × 行動
ビジネスコンプライアンス検定とは
コンプライアンスの知識・活用能力は、法務・コンプライアンス担当者だけでなく全てのビジネスパーソンに求められる知識です。
ビジネスコンプライアンス検定は、受け身の「法令遵守」にとどまらない「社会的要請に応えること」としての
コンプライアンスへの深い理解と活用能力を証明します。
ビジネスコンプライアンス検定は、受け身の「法令遵守」にとどまらない「社会的要請に応えること」としての
コンプライアンスへの深い理解と活用能力を証明します。

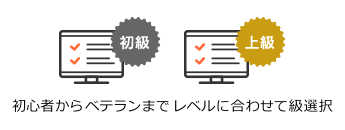
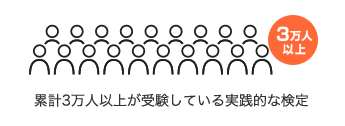
試験内容・学習について
健全な企業(組織)活動を推進するために必要となるコンプライアンス経営(法令・ルール・倫理等)およびビジネスパーソンとしてのコンプライアンス行動(法令・ルール・倫理等)について、その理念と目的の理解度、価値判断基準、および個々のビジネスシーンにおける対応能力を認定します。
初級
ビジネスパーソンとして日常業務を遂行する際に必要となる基礎的な法律知識と価値判断基準
上級
コンプライアンス経営の推進者および主体者として日々の業務課題の解決に取り組む、実践的な価値判断基準
BASIC
【団体受験のみ】
【団体受験のみ】
健全な社会生活を送る上で必要となる法令や社会規範など、コンプライアンスに関する基礎的な知識
ビジネスコンプライアンス検定
サンプル問題にチャレンジ!
上場企業A社のコンプライアンス・オフィサーX宛に、「公共営業部の社員Bが『公共工事の受注で談合をせざるを得ない。早く他の部署に異動したい』と言っていた」との匿名の文書が届いた。
この場合のXが最初にとるべき対応に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
この場合のXが最初にとるべき対応に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア
公共営業部に対して、緊急の内部監査を行う。
イ
公共営業部長に匿名文書を見せ、事実関係について聴取する。
ウ
匿名文書を公正取引委員会に送付する。
エ
社員Bから聴取する。
答え
【ウ】匿名文書を公正取引委員会に送付する。
コンプライアンス・オフィサーとして「最初にとるべき対応」は、社内の実情やコンプライアンス・プログラムの内容等に応じて様々であり、
選択肢ア、イ、エはいずれも、「最初にとるべき対応」として考え得るものである。
しかし、選択肢ウのように、情報の真実性について何の調査もせず、社内的にも何の了解もとらないで社内の違法行為に関する情報をいきなり当局に提供するというのは、
少なくとも企業に所属するコンプライアンス・オフィサーとしてとるべき対応ではない。
試験日程・受験方法
公開試験日程
第42回
2025年5月25日(日)
受付終了
第43回
2025年7月27日(日)
申込
受付中
受付中
資格受付ONLINEとは
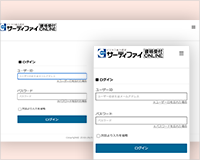
資格受付ONLINEは、試験の受験手続を行う総合サイトです。登録したアカウントは、資格受付ONLINE内で扱うすべての試験に共通でご利用いただけます。
- 受験申込・受験履歴・受験結果確認がすべてここで可能に
- デジタル問題集の購入・利用も可能
受験方法

「リモートWebテスト」による
在宅受験形式です。
在宅受験形式です。

検定の概要をまとめた
電子パンフレットを
ご用意しています。
電子パンフレットを
ご用意しています。
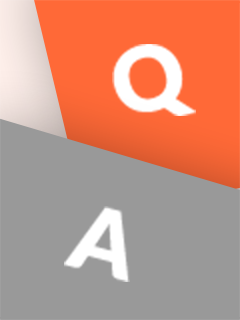
BASIC・初級・上級の
サンプル問題で
レベルをチェック!
サンプル問題で
レベルをチェック!
企業・各種法人等の団体単位で検定をご実施いただける
「団体受験制度」をご用意しています。
「団体受験制度」をご用意しています。





