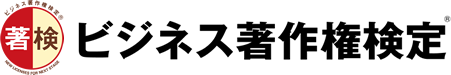創作活動を行っているクリエイターにとって、著作権侵害を巡るトラブルは身近な問題といえるでしょう。
「トレパク」とは、他人の絵や写真をトレース(上からなぞる)してパクる(盗む)という意味で使われている造語です。主にイラストレーターの界隈では悪い意味で使われていますが、常にトレースが違法となるわけではなく、その態様や程度によると考えられます。
本記事では、なぜトレパクがいけないのか、一体何をしたらトレパクになるのか、トレパクだと指摘されたらどう対応したらいいのかなどについて、詳しく解説します。
「トレパク」とは、他人の絵や写真をトレース(上からなぞる)してパクる(盗む)という意味で使われている造語です。主にイラストレーターの界隈では悪い意味で使われていますが、常にトレースが違法となるわけではなく、その態様や程度によると考えられます。
本記事では、なぜトレパクがいけないのか、一体何をしたらトレパクになるのか、トレパクだと指摘されたらどう対応したらいいのかなどについて、詳しく解説します。
当サイトを運営するサーティファイでは、ビジネス著作権検定を開催しており、企業の経営者・法務・総務のご担当者様やフリーランスのクリエイターの皆様が「意図しない著作権侵害を起こさないリテラシー」を身につけるためにご利用いただいています。
著作権の知識レベルを確かめる際に活用できる「検定の無料サンプル問題」を公開していますので、ぜひチェックしてみてください。
著作権の知識レベルを確かめる際に活用できる「検定の無料サンプル問題」を公開していますので、ぜひチェックしてみてください。
トレパクとは?
まずは、トレパクとは何なのか、トレパクの具体的な意味について確認しましょう。
特に、イラストやマンガ、デザインなどのクリエイティブな分野で問題とされることが多いようです。
トレースは、画力向上のための練習の一環として行われることもありますが、トレースした作品をそのまま公表することは著作権の侵害となる可能性があります。
そのような作品を作者に無断でトレースして(上からなぞって)制作した作品を自分の作品として発表するトレパクは、オリジナルの作者の努力やセンス、技術などにタダ乗りする行為です。オリジナルの作者の権利を侵害する行為として非難の対象にもなるでしょう。
さらに、トレパクによってオリジナルの作品の価値が下がるということも考えられるため、注意が必要です。
トレパクとは具体的に何を指すのか?
「トレパク」とは、「トレース」と「パクリ」という言葉を組み合わせた造語であり、他人の作品をトレースし、それを自分の作品として発表する行為を指します。特に、イラストやマンガ、デザインなどのクリエイティブな分野で問題とされることが多いようです。
トレースは、画力向上のための練習の一環として行われることもありますが、トレースした作品をそのまま公表することは著作権の侵害となる可能性があります。
トレパクが社会的に問題視される理由
ではなぜ、トレパクは社会的に問題視されるのでしょうか。 イラストやマンガなどのクリエイティブな作品には、作者の時間や努力、そして独自のセンスや技術、才能が反映されています。そのような作品を作者に無断でトレースして(上からなぞって)制作した作品を自分の作品として発表するトレパクは、オリジナルの作者の努力やセンス、技術などにタダ乗りする行為です。オリジナルの作者の権利を侵害する行為として非難の対象にもなるでしょう。
さらに、トレパクによってオリジナルの作品の価値が下がるということも考えられるため、注意が必要です。
著作権法とトレパクの関係
著作権法とトレパクには、どのような関係があるのでしょうか。ここからは、著作権の概要とトレパクとの関係性について解説します。
著作者は著作権に基づき著作物を独占的に利用できることから、第三者に著作物の利用を許諾する際に使用料などの経済的メリットを得ることができ、これが創作活動のインセンティブにもなります。
他人が著作権者の許諾を得ずにこれらの行為を行うと著作権侵害となりますので、注意しましょう。
具体的には、他人の作品を無断でトレースしてネット上で公開する行為は、上記の著作権の支分権のうち「複製権」や「翻案権」「公衆送信権」を侵害することになります。
しかし、明確な線引きは難しい面もあるでしょう。
著作権とは
まず、オリジナルの作者が作品について持っている著作権について確認しましょう。「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。
出典:公益社団法人著作権情報センター(はじめての著作権講座)
著作権法は、著作物を創作した著作者などに著作物の利用に関する独占的な権利を与えて保護を図りつつ、著作物の公正な利用を確保し、文化の発展に寄与することを目的としています。著作者は著作権に基づき著作物を独占的に利用できることから、第三者に著作物の利用を許諾する際に使用料などの経済的メリットを得ることができ、これが創作活動のインセンティブにもなります。
著作権の種類と内容
著作権法上、著作権は、以下の各権利(「支分権」といいます。)に細分化されています。他人が著作権者の許諾を得ずにこれらの行為を行うと著作権侵害となりますので、注意しましょう。
① 複製権
著作物のコピーを作成する権利です(著作権法第21条)。② 上演権・演奏権
著作物を公に直接見せたり聞かせたりすることを目的として、上演し、または演奏する権利です(著作権法第22条)。③ 上映権
著作物を公に上映する権利です(著作権法第22条の2)。④ 公衆送信権
著作物を公に向けて送信する権利です(著作権法第23条)。インターネット上に著作物をアップロードする行為などは、公衆送信権、送信可能化権によって保護されます。⑤ 口述権
言語の著作物を公に口述する権利です(著作権法第24条)。⑥ 展示権
美術の著作物または未発行の写真の著作物をこれらのオリジナル(原作品)により、公に展示する権利です(著作権法第25条)。⑦ 頒布権
映画の著作物を、配給フィルム・BD・DVDなどの複製物によって公衆に譲渡または貸与する権利です(著作権法第26条)。⑧ 譲渡権
著作物(映画の著作物を除く)のオリジナルまたは複製物を譲渡により、公衆に提供する権利です(著作権法第26条の2)。⑨ 貸与権
著作物(映画の著作物を除く)を、複製物の貸与(レンタル)により、公衆に提供する権利です(著作権法第26条の3)。⑩ 翻訳権・翻案権
著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化し、その他翻案する権利です(著作権法第27条)。出典:総務省e-Gov「著作権法」
著作権法とトレパクの関係性
著作権法は、作品の作者の権利を守るための法律です。トレパクはこの著作権法に抵触する可能性が高いと考えられます。具体的には、他人の作品を無断でトレースしてネット上で公開する行為は、上記の著作権の支分権のうち「複製権」や「翻案権」「公衆送信権」を侵害することになります。
しかし、明確な線引きは難しい面もあるでしょう。
トレパクが著作権侵害となる場合
では、どのような場合にトレパクは著作権侵害になるのでしょうか。その判断基準や、トレパクとほかのクリエイティブな行為との違いについて見ていきましょう。
しかし、トレースの範囲や公開の方法、その内容によっては著作権侵害とは認められない場合もあります。
まず、トレパクは基本的に他人の作品をトレースして(なぞって)コピーする行為を指します。一方、オマージュは過去の作品に敬意を表した作品を作ることを指し、インスピレーションは、ある作品から触発されて新しい作品を生み出すことをいいます。
すべてのケースにあてはまるわけではありませんが、考え方の目安として、オマージュの場合「有名な作品の有名なシーンと似た構図やセリフを用いることで、見た人に『元ネタ』が伝わることを前提とした演出効果」、 トレパクの場合「自分で一から描くよりもうまく、あるいは速く描くために、『元ネタ』を利用しており、『元ネタ』がバレることを想定していない」と捉えると、違いが分かりやすいかもしれません。
たとえば、ジョージ・ルーカス監督の「スター・ウォーズ」は、黒澤明作品のオマージュといわれている有名な映画です。
特に初心者がプロの作品を参考にすることで技術の向上を図ろうとする場合、トレースは非常に効果的な手段となります。
そして、練習のためにトレースを行うなど、個人的にまたは家庭内に限って使用することを目的とする場合には、私的使用として複製権侵害に該当しません(著作権法第30条第1項)。
また、他人が作成した画像をトレースし、それに手を加えて制作した作品を、著作権者に無断でインターネット上に公開した場合には、「翻案権」や「公衆送信権」の侵害に該当する可能性があるでしょう。 なお、判例上、翻案権侵害に該当するのは、その作品から、既存の作品の「表現上の本質的な特徴を直接感得できる場合」であるとされています。
著作権侵害の基準とトレパク
著作権侵害は、オリジナルの作品がオリジナリティ(創作性)を持っていることを前提として、他人がその作品に依拠して(参考にして)、 それと類似した作品を作者に無断で作成(複製)し、ネット上で公開(公衆送信)した場合などに成立します。一般に、トレパクは、この基準に当てはまることが多いでしょう。しかし、トレースの範囲や公開の方法、その内容によっては著作権侵害とは認められない場合もあります。
トレパクとオマージュ、インスピレーションの違い
トレパク、オマージュ、インスピレーション、これらは似たような行為のように思えますが、区別して考えるべきものです。まず、トレパクは基本的に他人の作品をトレースして(なぞって)コピーする行為を指します。一方、オマージュは過去の作品に敬意を表した作品を作ることを指し、インスピレーションは、ある作品から触発されて新しい作品を生み出すことをいいます。
すべてのケースにあてはまるわけではありませんが、考え方の目安として、オマージュの場合「有名な作品の有名なシーンと似た構図やセリフを用いることで、見た人に『元ネタ』が伝わることを前提とした演出効果」、 トレパクの場合「自分で一から描くよりもうまく、あるいは速く描くために、『元ネタ』を利用しており、『元ネタ』がバレることを想定していない」と捉えると、違いが分かりやすいかもしれません。
たとえば、ジョージ・ルーカス監督の「スター・ウォーズ」は、黒澤明作品のオマージュといわれている有名な映画です。
トレースの許容範囲
他人の作品をトレースすること自体は、イラスト制作の練習や技術向上の一環としては許容されることが多いでしょう。特に初心者がプロの作品を参考にすることで技術の向上を図ろうとする場合、トレースは非常に効果的な手段となります。
そして、練習のためにトレースを行うなど、個人的にまたは家庭内に限って使用することを目的とする場合には、私的使用として複製権侵害に該当しません(著作権法第30条第1項)。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
しかし、トレースした作品を公開する際は注意が必要です。オリジナルの作品をトレースしてそのまま無断で公開することは著作権侵害となり、違法となる可能性が高いといえます。また、他人が作成した画像をトレースし、それに手を加えて制作した作品を、著作権者に無断でインターネット上に公開した場合には、「翻案権」や「公衆送信権」の侵害に該当する可能性があるでしょう。 なお、判例上、翻案権侵害に該当するのは、その作品から、既存の作品の「表現上の本質的な特徴を直接感得できる場合」であるとされています。
トレパクによる著作権侵害のペナルティー
著作権法および民法には、権利侵害がなされたときの権利者による対抗措置や、侵害者に対する罰則などが定められており、トレパクが著作権侵害となる場合には、これらが適用されることになります。 トレパクによる著作権侵害のペナルティーを以下で確認しましょう。
これらの請求は、どれか1つということではなく、要件を満たせばそれぞれ請求可能です。
また、法人の従業員などがその業務に関して著作権侵害を行った場合には、その行為を行った従業員などに対して前述の刑罰が科せられるほか、法人に対しても「3億円以下の罰金」が科せられます(これを両罰規定といいます。著作権法第124条第1項)。
また、法人が告訴された場合には、違反行為をした従業員個人も告訴されたことになり、違反行為をした従業員個人が告訴された場合には、法人も告訴されたことになります(著作権法第124条第3項)。
もっとも、著作権侵害は親告罪であるため、被害者である権利者からの告訴がない限り起訴されません(著作権法第123条第1項)。ただし、一部例外があります。
民事上の対抗措置
権利者は、民事では、侵害者に対して次の4つの対抗措置をとることができます。これらの請求は、どれか1つということではなく、要件を満たせばそれぞれ請求可能です。
差止請求
権利者(著作者、著作権者、出版権者、実演家または著作隣接権者)は権利を侵害する者や侵害するおそれのある者に対して、侵害の停止または予防を請求することができます(著作権法第112条)。出典:総務省e-Gov「著作権法」
損害賠償請求
さらに、権利者は民法に基づいて損害賠償請求もできますが(民法第709条)、その具体的な損害額を立証しなくても、侵害者による複製物の数量に利益額を乗じた額を権利者が受けた損害とすることができる等とされています(著作権法第114条)。出典:総務省e-Gov「民法」
出典:総務省e-Gov「著作権法」
不当利得返還請求
著作権侵害行為によって侵害者が利益を受けている場合は、権利者は侵害者に対して、その利益を返還するよう請求することができます(民法第703条、第704条)。この不当利得返還請求は、上記の損害賠償請求権が3年の消滅時効にかかってしまった場合の代替手段として利用されることが多いといわれています。出典:総務省e-Gov「民法」
名誉回復等の措置
最後に、著作者等は、故意または過失によりその著作者人格権等を侵害した者に対して、名誉や声望を回復するための措置(謝罪広告の掲載など)を請求することができます(著作権法第115条)。出典:総務省e-Gov「著作権法」
刑事上の処罰
他人の著作権を侵害する行為は犯罪ですので、上記のような民事上の措置だけではなく、権利者が告訴することによって(親告罪。一部例外あり)、侵害者に刑罰が科せられる場合があります。著作権の侵害
著作権侵害の場合、罰則は「10年以下の懲役」または「1000万円以下の罰金」となります。しかも、どちらか一方ではなく懲役と罰金の両方が科せられる場合があることも理解しておきましょう(著作権法第119条第1項)。また、法人の従業員などがその業務に関して著作権侵害を行った場合には、その行為を行った従業員などに対して前述の刑罰が科せられるほか、法人に対しても「3億円以下の罰金」が科せられます(これを両罰規定といいます。著作権法第124条第1項)。
また、法人が告訴された場合には、違反行為をした従業員個人も告訴されたことになり、違反行為をした従業員個人が告訴された場合には、法人も告訴されたことになります(著作権法第124条第3項)。
もっとも、著作権侵害は親告罪であるため、被害者である権利者からの告訴がない限り起訴されません(著作権法第123条第1項)。ただし、一部例外があります。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
トレパクに関する最近の事例
ここからは、最近生じた「トレパク」を巡る騒動をご紹介します。
古塔さんは、Twitter(現X)で「引用・オマージュ・再構築として制作した一部の作品を、権利者の許諾を得ずに投稿・販売してしまったことは事実」「写真そのものをトレースしたことはございません。模写についても盗用の意図はございません」と釈明し、トレパクや盗用は否定。結果として、古塔さんの作品集の出荷停止、コラボTシャツの販売停止などの事態に至りました。
有名イラストレーターのトレパク疑惑
音楽ユニット「YOASOBI」のキービジュアルを担当したイラストレーターの古塔つみさんについて、既存の写真などをトレースして描く「トレパク」疑惑が指摘され、問題になったことがあります。古塔さんは、Twitter(現X)で「引用・オマージュ・再構築として制作した一部の作品を、権利者の許諾を得ずに投稿・販売してしまったことは事実」「写真そのものをトレースしたことはございません。模写についても盗用の意図はございません」と釈明し、トレパクや盗用は否定。結果として、古塔さんの作品集の出荷停止、コラボTシャツの販売停止などの事態に至りました。
トレパクだと非難されるのを防ぐための対策や注意点とは
ここからは、クリエイターがトレパクだと非難されるリスクを回避し、自分の身を守るための方法について解説します。
著作権法の知識をしっかりと理解し身につけることで、トレパクだと誤解されるリスクを低減することができます。
意図せず他人の作品に似てしまい、トレースや模倣をしたと非難されるのを避けるためには、定期的に自分の作品を見直し、他人の作品との類似点がないか確認することも考えられます。
また、作品を制作する過程を動画に撮影しておくことも有用でしょう。CGの場合、イラスト制作アプリケーションの中には「自動で制作過程の画面を記録し、タイムラプス動画を作成できる」機能が搭載されているものもあります。
公開されている作品でも、基本的には著作権により保護されていますので、無断での使用や複製は著作権侵害となる可能性があります。したがって、公開作品を参考にする場合も、複数の作品を参考にしながら、自分独自の解釈やアレンジを加えてオリジナリティーを持たせることで、トレパクと指摘されるリスクを小さくすることができるでしょう。
なお、ネット上ではトレスフリー素材なども公開されていますので、それらは、利用条件などを確認の上、トレースして利用することができます。
著作権侵害とまではいえないケースでも、道義上の問題として厳しい目が向けられる傾向が強まっているようですので、どのようなケースが問題視されているかを知ることは、風評リスクを避けるために大切です。
クリエイターコミュニティー内では、トレパクを行うことのリスクや問題点が広く共有されており、SNS上でもトレパクに関する議論や情報交換が活発に行われているようです。
このような情報を積極的に収集し、最新の動向を把握して正しい知識を身につけることで、トレパクのリスクをさらに低減することができます。
著作権に関する基礎知識を身につける
トレパクだと非難されないためには、まず著作権に関する基礎的な知識を身につけることが重要です。著作権法の知識をしっかりと理解し身につけることで、トレパクだと誤解されるリスクを低減することができます。
オリジナル作品の作成時の注意点
まず、オリジナル作品を作成する際には、他のクリエイターの作品との類似性を常に意識することが大切です。意図せず他人の作品に似てしまい、トレースや模倣をしたと非難されるのを避けるためには、定期的に自分の作品を見直し、他人の作品との類似点がないか確認することも考えられます。
また、作品を制作する過程を動画に撮影しておくことも有用でしょう。CGの場合、イラスト制作アプリケーションの中には「自動で制作過程の画面を記録し、タイムラプス動画を作成できる」機能が搭載されているものもあります。
他人の作品を参考にする際のポイント
他のクリエイターの作品を参考にすることもあると思いますが、その際には、その作品の著作権や使用許諾の状況を確認することが重要です。公開されている作品でも、基本的には著作権により保護されていますので、無断での使用や複製は著作権侵害となる可能性があります。したがって、公開作品を参考にする場合も、複数の作品を参考にしながら、自分独自の解釈やアレンジを加えてオリジナリティーを持たせることで、トレパクと指摘されるリスクを小さくすることができるでしょう。
なお、ネット上ではトレスフリー素材なども公開されていますので、それらは、利用条件などを確認の上、トレースして利用することができます。
トレパクに関する情報収集を行う
近年、「トレパク」に対する社会的な認識は高まっています。著作権侵害とまではいえないケースでも、道義上の問題として厳しい目が向けられる傾向が強まっているようですので、どのようなケースが問題視されているかを知ることは、風評リスクを避けるために大切です。
クリエイターコミュニティー内では、トレパクを行うことのリスクや問題点が広く共有されており、SNS上でもトレパクに関する議論や情報交換が活発に行われているようです。
このような情報を積極的に収集し、最新の動向を把握して正しい知識を身につけることで、トレパクのリスクをさらに低減することができます。
トレパクと非難されたときの対処法
クリエイターの皆さんが日々作品を創作し公表していると、トレパクしたとの誤解や疑惑に直面することもあるでしょう。ここでは、トレパクを疑われたときの対処法について説明します。
また、自分の作品の制作過程の記録や参考にした資料など、証拠となるものを整理することも重要なポイントになります。
誤解や疑いを解消するために、誠実な態度で話し合いを行うことによって、誤解を解くことができるかもしれません。先ほど述べた証拠資料などが整理してあると、このような話し合いもスムーズに進むと思われます。
著作権に詳しい専門家や、クリエイターコミュニティーのメンバーなどから、客観的な意見をもらうことで、解決の糸口が見つかるかもしれません。
著作権に関する訴訟は専門的な知見を要するものであり、十分な知識や準備が必要です。
ところで、トレパクに関する訴訟として、最近、トレパクされたと公然と非難した側が、逆に、名誉棄損を理由に損害賠償を命じられたという事案がありました。
このように、他人に対して、不用意に「トレパクだ」と指摘するのはリスクのある行為です。「トレパクされたかも?」と思った場合でも、軽率な言動は控え、十分な事実確認や情報収集を行った上で、必要があれば法律の専門家などに相談しましょう。
冷静に事実関係を確認する
トレパクしたと疑われた場合、感情的になって拙速に反応するのではなく、まずは冷静に事実関係を確認しましょう。自分の作品が他人の作品と、どこが、どのように似ているのか、具体的に確認することが大切です。また、自分の作品の制作過程の記録や参考にした資料など、証拠となるものを整理することも重要なポイントになります。
直接コミュニケーションを取る
疑念を持たれた相手や第三者との間で、直接コミュニケーションを取ることも考えられます。誤解や疑いを解消するために、誠実な態度で話し合いを行うことによって、誤解を解くことができるかもしれません。先ほど述べた証拠資料などが整理してあると、このような話し合いもスムーズに進むと思われます。
利害関係のない第三者の意見を求める
利害関係のない第三者から意見やアドバイスをもらうのも有益でしょう。著作権に詳しい専門家や、クリエイターコミュニティーのメンバーなどから、客観的な意見をもらうことで、解決の糸口が見つかるかもしれません。
必要に応じて法的対応を考える
そして、当事者同士での対話や交渉だけで問題が解決しない場合には、専門家に相談し、法的手段をとることも考えざるを得ません。著作権に関する訴訟は専門的な知見を要するものであり、十分な知識や準備が必要です。
ところで、トレパクに関する訴訟として、最近、トレパクされたと公然と非難した側が、逆に、名誉棄損を理由に損害賠償を命じられたという事案がありました。
出典:裁判所HP(東京地方裁判所裁判例) 東京地方裁判所令和2年(ワ)第25439号(本訴)、令和3年(ワ)第1631号(反訴)
この事件では、あるイラストレーターAが、自分の管理するブログやツイッターで「他のイラストレーターBが自分の作品をトレースしてイラストを作成した」と非難した行為が名誉毀損行為であると認定され、イラストレーターAは慰謝料200万円などの損害賠償を命じられました。このように、他人に対して、不用意に「トレパクだ」と指摘するのはリスクのある行為です。「トレパクされたかも?」と思った場合でも、軽率な言動は控え、十分な事実確認や情報収集を行った上で、必要があれば法律の専門家などに相談しましょう。
著作権に対する理解度を確かめよう
イラストなどの画像には著作権が認められ、著作権者に無断で複製・アップロード・パロディー化などを行うと著作権侵害に該当することがあります。
著作権侵害を起こさないために必要な知識などが備わっているかどうか、ビジネス著作権検定の試験問題にチャレンジして確かめてみましょう。
著作権侵害を起こさないために必要な知識などが備わっているかどうか、ビジネス著作権検定の試験問題にチャレンジして確かめてみましょう。
ビジネス著作権検定では以下のような問題が出題されます
許諾なく利用できる場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア
入学試験の問題に著作物を利用する場合は、入学試験の特性に鑑み、著作者に事前に通知する必要はないが、事後には通知しなければならない。
イ
入学試験に必要な場合は、試験の実施者は、著作物の複製だけでなく、公衆送信を行なうことができる場合がある。
ウ
学校の入学試験だけでなく、会社の入社試験のために必要な場合であっても、著作物を複製して利用できる場合がある。
エ
学校の入学試験だけでなく、予備校の模擬テストのために必要な場合であっても、著作物を複製して利用できる場合がある。
このような問題を「サンプル問題」として一部公開しています。著作権に関するインプット、検定のイメージをつかむためにぜひご活用ください。
(先ほどのクイズは「ア」が正解です)
執筆者プロフィール
尾原央典
2002年弁護士登録。一般企業法務(顧問弁護士業務)を中心に、紛争解決(訴訟、交渉等)、不動産、相続、法人・個人の倒産等、幅広く民事・商事を取り扱う。
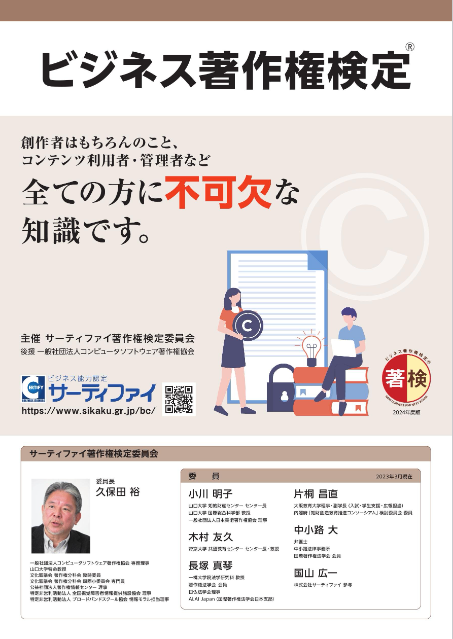
検定の概要をまとめた
電子パンフレットを
ご用意しています。
電子パンフレットを
ご用意しています。

ビジネス著作権検定の
サンプル問題を
掲載しています。
サンプル問題を
掲載しています。