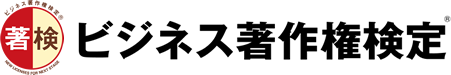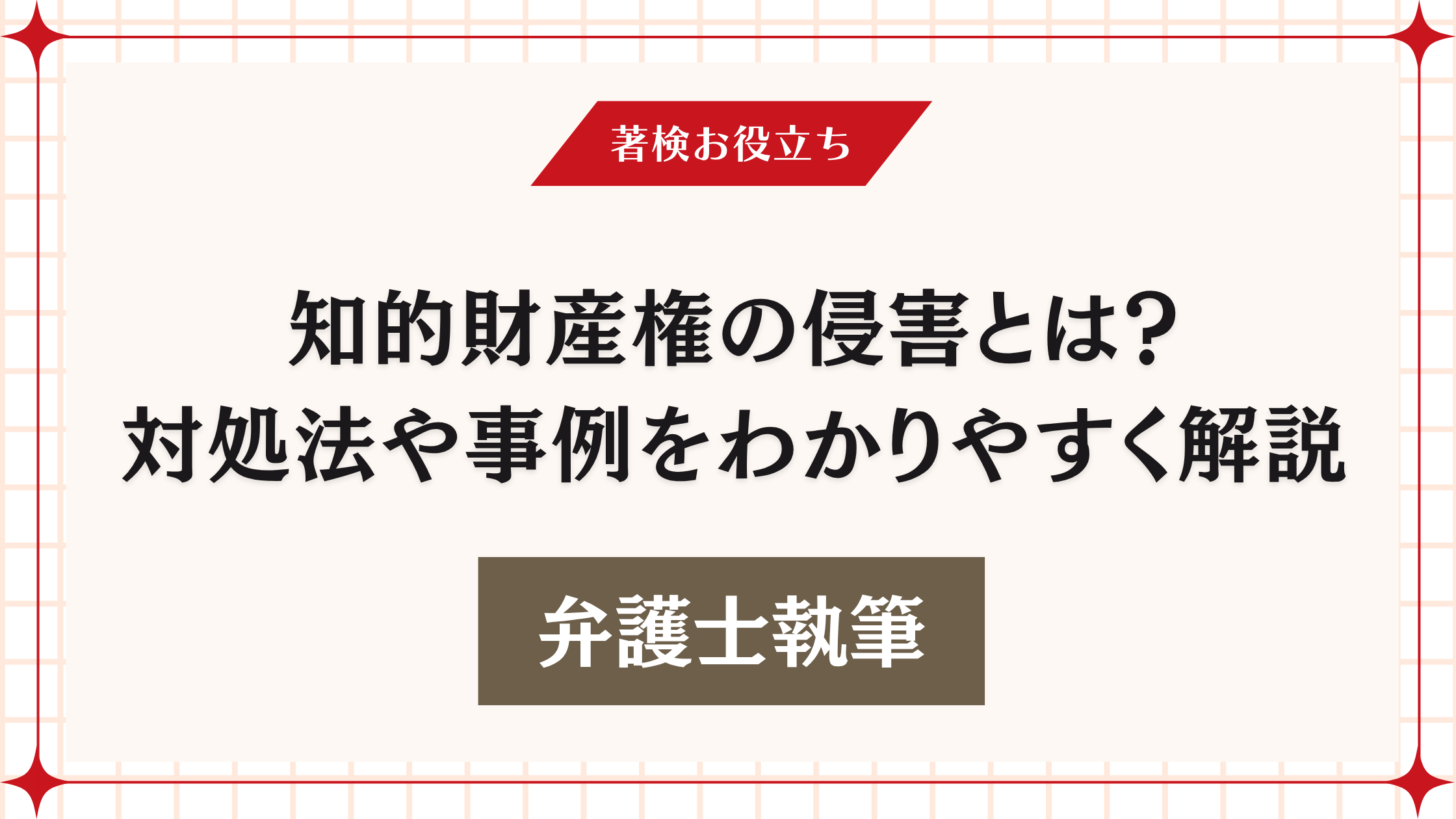
企業における知的財産権の活用の重要性は年々高まっています。自社の知的財産権を第三者に侵害された場合、対応せずに放置していると、売上減少などの思わぬ被害が拡大してしまうおそれがあります。早急に対策を講じることが大切です。
では、自社の知的財産権を侵害された場合には、どのように対応すればよいのでしょうか?また、自社の業務にあたって他社の知的財産権を侵害してしまわないためには、どのような予防策を講じればよいのでしょうか?
この記事では、著作権、特許権、意匠権などについて知的財産権の侵害の事例をご紹介した上で、自社が侵害行為の被害に遭った際の対処法や、自社が侵害しないための対策などについて解説します。
では、自社の知的財産権を侵害された場合には、どのように対応すればよいのでしょうか?また、自社の業務にあたって他社の知的財産権を侵害してしまわないためには、どのような予防策を講じればよいのでしょうか?
この記事では、著作権、特許権、意匠権などについて知的財産権の侵害の事例をご紹介した上で、自社が侵害行為の被害に遭った際の対処法や、自社が侵害しないための対策などについて解説します。
当サイトを運営するサーティファイでは、ビジネス著作権検定を開催しており、企業の経営者・法務・総務のご担当者様やフリーランスのクリエイターの皆様が「意図しない著作権侵害を起こさないリテラシー」を身につけるためにご利用いただいています。
著作権の知識レベルを確かめる際に活用できる「検定の無料サンプル問題」を公開していますので、ぜひチェックしてみてください。
著作権の知識レベルを確かめる際に活用できる「検定の無料サンプル問題」を公開していますので、ぜひチェックしてみてください。
知的財産権の侵害とは?
知的財産権の侵害とは、他人または他社の知的財産権を侵害する行為を指します。まずは、知的財産権について理解しておきましょう。
知的財産権とは
人間の知的な創作活動によって生み出されたアイデアや創作物などには、財産的な価値を持つものがあり、そうしたものを総称して「知的財産」と呼びます。また、知的財産の中には著作権や、商標権、特許権など、法律で権利として保護されるものがあり、それらの権利は「知的財産権」と呼ばれます。知的財産権を侵害した場合の罰則等
知的財産権の侵害に対しては、法律上、権利者による損害賠償請求や差し止め請求が認められています。また、故意による知的財産権の侵害について法律上刑事罰も定められているため注意が必要です。例えば、著作権の侵害については、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります(法人については3億円以下の罰金)。特許権や商標権の侵害についても同様の刑事罰が定められています。出典:総務省e-Gov「著作権法」
知的財産権の種類
知的財産権には、大きく分けて、著作権、産業財産権、その他の権利があります。
このうち、著作権は、著作権法に基づき、著作物を保護する権利です。著作物は人間の知的・精神的活動の所産であり、文化の形成と発展の基盤をなすものであるという観点から、「文化の発展」を目的に、著作物の創作者の権利が保護されています。この著作権は、国への登録などを経なくても、著作物がつくられた時点で自動的に発生します。
これに対し、産業財産権は、主に企業活動にかかわる知的財産権です。特許権、商標権、意匠権、実用新案権の4つがあり、その概要は以下のとおりです。
・特許権:発明を保護する権利
・商標権:ロゴマークやブランド名を保護する権利
・意匠権:工業デザイン等を保護する権利
・実用新案権:物品の形状等の考案を保護する権利
これらの産業財産権は、著作権とは異なり、特許庁に出願し、登録されなければ、発生しません。
そのほかの知的財産権には、半導体の回路配置を保護する回路配置利用権や、植物の新品種を保護する育成権、営業秘密などを保護する不正競争法上の利益などが挙げられます。
このうち、著作権は、著作権法に基づき、著作物を保護する権利です。著作物は人間の知的・精神的活動の所産であり、文化の形成と発展の基盤をなすものであるという観点から、「文化の発展」を目的に、著作物の創作者の権利が保護されています。この著作権は、国への登録などを経なくても、著作物がつくられた時点で自動的に発生します。
これに対し、産業財産権は、主に企業活動にかかわる知的財産権です。特許権、商標権、意匠権、実用新案権の4つがあり、その概要は以下のとおりです。
・特許権:発明を保護する権利
・商標権:ロゴマークやブランド名を保護する権利
・意匠権:工業デザイン等を保護する権利
・実用新案権:物品の形状等の考案を保護する権利
これらの産業財産権は、著作権とは異なり、特許庁に出願し、登録されなければ、発生しません。
そのほかの知的財産権には、半導体の回路配置を保護する回路配置利用権や、植物の新品種を保護する育成権、営業秘密などを保護する不正競争法上の利益などが挙げられます。
知的財産権の侵害
知的財産権の侵害とは、他人または他社の知的財産を無断で利用する行為などをいいます。主な知的財産権について、侵害行為の例は、以下のとおりです。
著作権の侵害
著作権の侵害は、著作権の対象となっている著作物を著作権者に無断で転載したり、インターネット上にアップロードしたりする行為が典型例です。そのほかにも、たとえば、他人の著作物を加工して別の著作物を作成する行為や、他人の著作物を公衆に直接見せまたは聞かせることを目的として上演したり、演奏したりする行為も、著作権の侵害にあたります。特許権の侵害
特許権の侵害とは、特許権者に無断で、特許権の登録がされている発明を業として「実施」する行為などがこれにあたります。例えば、物を生産する方法について特許の登録がされている場合に、特許権者に無断でその方法を生産に使用したり、その方法で生産した物を販売したりする行為が特許権侵害にあたります。商標権の侵害
商標権の侵害とは、商標登録された他社のロゴマークやブランド名を無断で使用する行為をいいます。ただし、商標権は、商品やサービスを指定して登録されるものであり、商標権者に対して、商標登録したロゴマークやブランド名を、分野を問わず独占的に使用する権利を与えるものではありません。そのため、商標権者が登録時に指定した商品やサービスと同一または類似する商品やサービスについて、他社がこれを無断で使用した場合にのみ、商標権侵害となります。意匠権の侵害
意匠権の侵害は、意匠登録されたデザインやこれに類似するデザインで物品を製造したり販売したりする行為が典型例です。類似しているかどうかの判断は、「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う」とされています(意匠法24条2項)。出典:総務省e-Gov「意匠法」
身近に潜む知的財産権の侵害にあたるケース
以下では、身近な行為の中で、知的財産権の侵害にあたる可能性があるものをご紹介します。
YouTubeなど、動画投稿サービスがJASRAC等と利用許諾契約を締結している場合もあり、自ら演奏または制作したもの等については、一定の条件のもと、投稿ユーザー側で手続きをすることなく楽曲を利用できる場合もあります。
楽曲の無断利用
たとえば自分が撮影した動画に、無断で有名アーティストの楽曲をBGMとして入れてインターネット上にアップロードする行為は、著作権侵害にあたります。一般社団法人日本音楽著作権協会(通称:JASRAC)などの著作権管理団体に許諾を得た上で使用料を支払って使用する必要があります。YouTubeなど、動画投稿サービスがJASRAC等と利用許諾契約を締結している場合もあり、自ら演奏または制作したもの等については、一定の条件のもと、投稿ユーザー側で手続きをすることなく楽曲を利用できる場合もあります。
画像の利用
たとえば、他人がインターネット上で公開している画像を無断で自分のサイトに転載する行為は、著作権侵害にあたります。画像の著作権者の許諾を得た上で使用する必要があります。商品デザインの模倣
事業主の立場で気をつけたいのが、商品デザインの模倣です。その商品デザインについて意匠権がとられていれば意匠権侵害にあたる可能性があります。また、意匠権がとられていない場合でも、不正競争防止法違反や著作権侵害に該当することがあるため、注意が必要です。企業における知的財産権の侵害について事例を紹介
企業にとって、自社が保有している知的財産権は非常に重要な経営資源であり、知的財産権の侵害をめぐって紛争に発展する例も少なくありません。以下で、いくつか事例をご紹介します。
著作権に関する漫画村事件
漫画村事件とは、無料で閲覧可能な海賊版サイトに、人気漫画の違法コピーが大量に公開された事件です。複数の出版社が刑事告訴を行った結果、2021年6月、主犯格である男性に対して著作権法違反の罪で懲役3年、罰金1000万円、追徴金6257万1336円の実刑判決が下されました。また、アップロード行為などを行った実行役に対しても、有罪判決が下されました。サトウの切り餅の特許権侵害訴訟
「サトウの切り餅事件」は、切り餅の表面に切り込みを入れる技術について特許権を取得していた越後製菓が、佐藤食品工業が販売する「サトウの切り餅」により特許権が侵害されたと主張し、製造販売差し止めや損害賠償を求めた裁判です。知的財産高等裁判所の判決により、佐藤食品工業は、8億円を超える損害賠償を命じられました。本田技研工業のバイクの意匠権侵害訴訟
オートバイクで知られるホンダ(本田技研工業株式会社)は、代表車種である「スーパーカブ」のデザインに関して意匠権を取得し、模造品の排除に取り組んできました。ホンダはデザインを模倣したオートバイを製造・販売した企業に対し、意匠権の侵害に基づく損害賠償請求などの訴訟を起こし、裁判所は、侵害企業に対し、7億円を超える損害賠償を命じています。知的財産権侵害の対処法は?
自社が知的財産権を侵害された場合の対処法は、大きく分けて、差し止め請求・損害賠償請求・刑事告訴の3通りがあります。
差し止め請求をする
差し止め請求とは、知的財産権の侵害にあたる行為をやめるように、侵害者に対して請求することをいいます。著作権の侵害の場合は、著作物の無断使用を停止することのほか、著作権を侵害して作成された模造品や海賊版がある場合はその廃棄を請求することも可能です。商標権や意匠権、特許権といった産業財産権の侵害の場合は、知的財産権を侵害している製品の製造・販売を禁止し、すでにある在庫を廃棄することなどを請求することができます。これらの請求に侵害者が応じない場合は、訴訟等の手段をとることにより、裁判所の判決で、侵害者に対して差し止めを命じてもらうことも可能です。損害賠償請求をする
知的財産権の侵害は、民法上の不法行為に該当するため、被害者は侵害者に対して損害賠償を請求できます。これについても、侵害者が損害賠償に応じない場合は、訴訟等の手段をとることになります。刑事告訴をする
知的財産権の侵害には、刑事罰が設けられている場合もあります。侵害者が故意で自社の知的財産権を侵害しているケースなどでは、警察や検察に対して刑事告訴を行い、刑事罰を科すように求めることが可能です。知的財産権を侵害しないための対策とは?
自社が業務を遂行するにあたって、他社の知的財産権を侵害しないように注意することも重要です。たとえば、次のような対策を講じるとよいでしょう。
ビジネス著作権検定は、知的財産権の中でも多くの人にとって身近な著作権に特化した検定試験です。実務経験などの受験資格も定められていないため、誰でもチャレンジすることができます。
また、ビジネス著作権検定の上級に合格すると、国家資格である「知的財産管理技能検定」の2級の受験資格を得ることができます。このように、従業員の知識レベルに応じた試験の受験を奨励することで、明確な目標を持った知識習得が可能になるでしょう。
新製品を計画する際は必ず他社の知的財産権を調査する
新製品の製造や販売を計画するときは、他社の特許権や実用新案権、商標権、意匠権などの産業財産権を侵害しないかどうか、事前に調査することが必要です。これらの権利は、知的財産データベースの「特許情報プラットフォーム」で調べることができます。知的財産権について理解を深める
知的財産権についての誤った認識から、他人または他社の知的財産権を侵害してしまう例も少なくありません。誤解から侵害行為を行ってしまうことのないように、知的財産権について理解を深めておくことが必要です。従業員に対して知的財産権に関する研修を行う
知的財産権について経営陣のみが理解していたとしても、従業員の誤った認識から侵害をしてしまうリスクがあります。そのため、知的財産権について、従業員向けの研修などを行うことが適切です。従業員の知識研鑽を奨励する
従業員に資格試験の受験を勧めるなどして、知的財産権の分野についての知識研鑽を奨励することも有効な取り組みの一つです。知的財産権に関する資格・検定試験として、国家試験の「弁理士試験」「知的財産管理技能検定」や、民間試験の「ビジネス著作権検定」などがあります。ビジネス著作権検定は、知的財産権の中でも多くの人にとって身近な著作権に特化した検定試験です。実務経験などの受験資格も定められていないため、誰でもチャレンジすることができます。
また、ビジネス著作権検定の上級に合格すると、国家資格である「知的財産管理技能検定」の2級の受験資格を得ることができます。このように、従業員の知識レベルに応じた試験の受験を奨励することで、明確な目標を持った知識習得が可能になるでしょう。
著作権について効率よく学ぶなら
企業の担当者やクリエイターとして、自社や自身が著作権侵害をするリスクがないか、ビジネス著作権検定の試験問題にチャレンジして確かめてみましょう。
ビジネス著作権検定より問題
A社は、自社のイメージキャラクター画のデザインをデザイナーのBに依頼した。この事例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア
A社とデザイナーBの間の委託契約で著作権に関する合意が何らなされていなくても、A社が自社のイメージキャラクターのデザインをデザイナーBに頼んだ以上、報酬が支払われた時点で、A社がそのイメージキャラクターの著作権を取得したと推定される。
イ
A社とデザイナーBの間で、デザイナーBがデザインしたイメージキャラクターについて「著作権のすべてをA社に譲渡する。」という契約を締結した場合、A社は著作権者になっているのだから、そのイメージキャラクターのデザインを翻案することができる。
ウ
デザイナーBがデザインしたイメージキャラクターの翻案権を契約でA社が 得た場合であっても、A社はそのイメージキャラクターのデザインをデザイナー Bの意思に反して改変することはできない。
エ
デザイナーBから著作権の譲渡を受けたA社が、その後経営不振により解散した場合、当然にその著作権は著作者であるデザイナーBに戻る。
クイズ形式で著作権に関するリテラシーを効率的にUPしたい場合は、ビジネス著作権検定を受けてみてください。
こちらから、サンプル問題を無料DLできます
こちらから、サンプル問題を無料DLできます
(先ほどのクイズは「ウ」が正解です)
執筆者プロフィール
西川暢春(にしかわのぶはる)
東京大学法学部卒業。大阪弁護士会登録。現在、弁護士法人咲くやこの花法律事務所代表弁護士。企業の顧問弁護士を多数務める。知的財産の処理を踏まえた人事労務制度の整備などを取扱い分野とする。著書に「労使トラブル円満解決のための就業規則・関連書式作成ハンドブック」(日本法令)などがある。
弁護士法人咲くやこの花法律事務所HP
(企業法務に強い弁護士の法律相談サービス、顧問弁護士サービスなど)
弁護士法人咲くやこの花法律事務所HP
(企業法務に強い弁護士の法律相談サービス、顧問弁護士サービスなど)
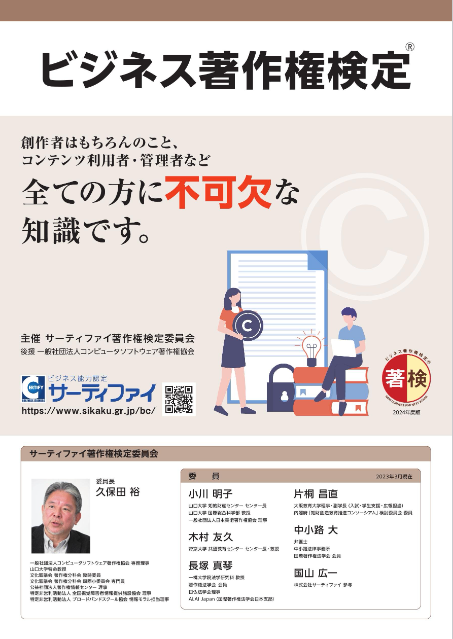
検定の概要をまとめた
電子パンフレットを
ご用意しています。
電子パンフレットを
ご用意しています。

ビジネス著作権検定の
サンプル問題を
掲載しています。
サンプル問題を
掲載しています。